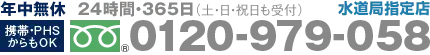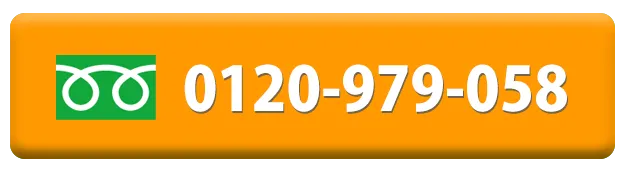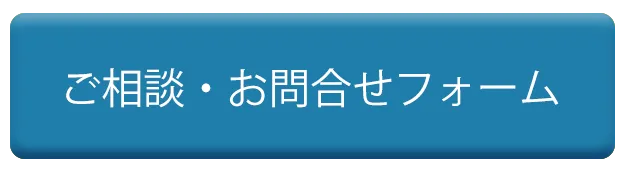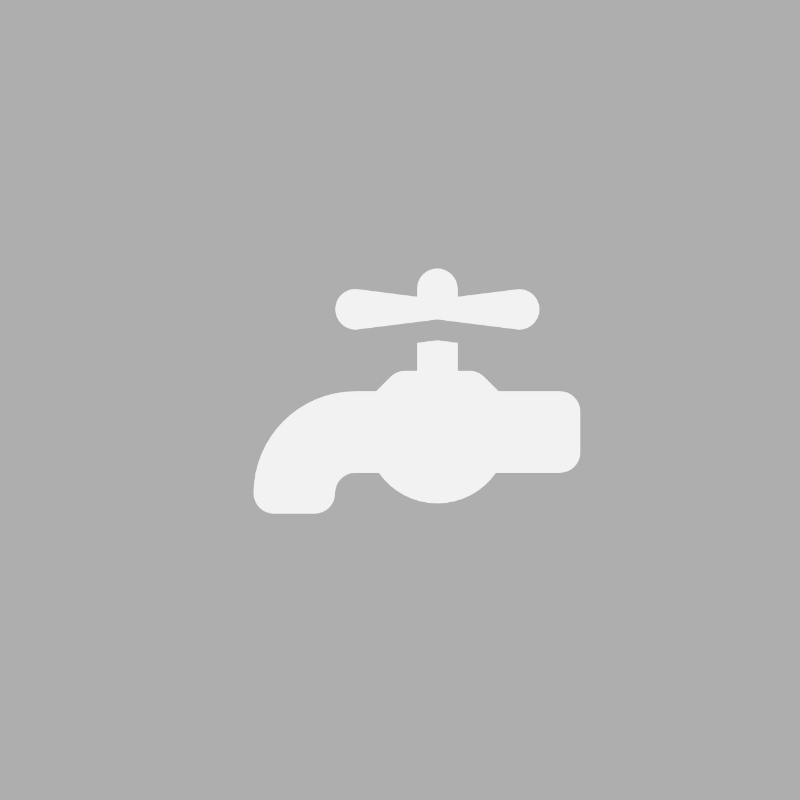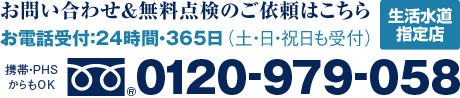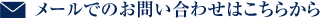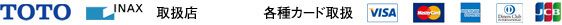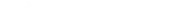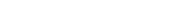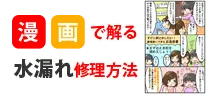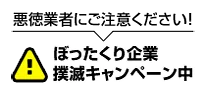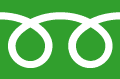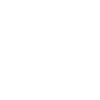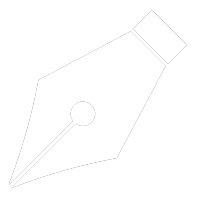
- 投稿日: 2022/06/03
- 更新日: 2024/05/29
洗濯機の取り付けは自分でできる?簡単5ステップ
家電のリフォームや買い替えを検討している方に向けて、洗濯機の取り付けに関する全面ガイドを提供します。新しい機種を選ぶ際は、メーカーの推奨するスペックや、設置場所のコンセントと排水トラップの位置を確認し、適切な工具で確実に施工することが重要です。また、狭いスペースやベランダに設置する場合、通常の置き場所とは異なる特殊な工夫が必要です。この記事では、別売りの部品を使用したり、別途ハウスクリーニングや清掃を行う方法など、異なる状況に合わせた選び方や試運転の目安についても詳しく説明します。さらに、ドアや窓を外す作業や、2人で行う施工の手順も合わせて紹介し、万が一の問題を防ぐための方針についても触れます。エアコンや乾燥機と同様、洗濯機の取り付けは生活に欠かせないため、事前にしっかりと準備を行うことが、快適で気軽な暮らしを送るための鍵となります。
目次
知人からもらった洗濯機を部屋へ設置したい
ネットで格安のものを買い、自分でセッティングしたい
自分でとりつけたいけど、ちゃんとできるかが心配
こんなことで悩んでおられませんか。
私は
・水まわりに関することなら何でもOK!のプロの集まり
・水についての「困った」を解決しつづけてもうすぐ30年
こんな会社の現場担当社員として、長年お客様が持つお悩みと向き合っています。
この記事は、

・業者を使わずに自分で洗濯機をセッティングする手順
・自分でセッティングを行う際に注意すべきこと
・自分でセッティングした際に起こりがちなトラブルとその対処法
について、押さえるべきコツ及びやりかたを述べていきます。
先に結論を言うと、洗濯機を専門家の手を借りないで設置するのなら、それなりに
知識や搬入経路のコツが
必要でしょう。しかし、これから述べるポイントさえ押さえれば、だれにでも簡単に
洗濯機のセッティングができるんですよ。
こちらの記事を最後まで読んだら、あなたはもうこんな心配はなくなります。
・高さセッティングに大失敗。せっかく買った洗濯機も使えない
・排水がうまくいかず、部屋中水浸しとなる
・セッティングがうまくいかず、その後依頼した業者に高額請求された
こんなことにはもうバイバイしませんか。
この記事を読むだけで誰にでもできるので、どうか最後まで読んでください!
1.もしも設置をミスったら?

2.設置は自分でできるの?
「洗濯機の設置って、自分一人でできるの?」 この問いにおける答えは 「ケース・バイ・ケースです」 となるでしょう。 なぜなら、 洗濯機はコンパクトなものでも30キロ以上 、ファミリータイプのドラム式などでは 80キロを超えるものもあるからです。 こうなると、たとえあなたがどれだけ力持ちだとしても、一人で運びきるのはキツイです。それだけでなく一人の作業はとても危ないので、必ず複数で行いましょう。 ただし、業者さんや友人たちなどが防水パンのところまで持ってきてくれる。さらに洗濯機の位置調整が不要ならば、一人でもセッティングは可能なのです。 助っ人を呼ぶかどうか。これはおのおのが置かれる状況によって判断するとよいでしょう。3.設置前はここをチェック

3.1 セッティング場所の安定性
最初に、本体を置くための 適したセッティング場所 が存在するかチェックしましょう。一般的に、新しいタイプの集合住宅等には専用のスペースが備わっていることが多いです。しかし、一方で築年数が経過している集合住宅や一軒家などは、特にしっかりとこうした場所の安定性を確かめる必要があるでしょう。3.1.1 風雨や湿気にさらされないか
洗濯機は家電なので、屋外で屋根がない場所といった 雨や風 にさらされやすいところ、あるいは極端に湿気が高いところへの設置によって、トラブルを招きやすくなります。また 寒冷地における屋外設置 も、本体が凍結してしまう可能性があるので回避するべきです。3.1.2 地面は水平で安定しているか
設置するスポットにおける床などがかたむいておらず、ちゃんと水平になっているかも確認しましょう。水平な場所に設置できないと、後々ガタガタとした 振動や騒音 を引き起こすかもしれません。必要があれば防音マットや洗濯機の脚などを用いて調整しましょう。3.1.3 排水溝などが確保できるか
洗濯機には洗濯で使用した水を排出する所が必要になります。この排水口がちゃんとあるか確かめましょう。場合にとっては排水ホース延長や防水パンかさ上げなどが必要になります。3.2 玄関からの搬入スペース
設置場所がこれでOKだと判明したら、次にそこまで運んでいくことができるかも確かめましょう。 屋外なら問題ないですが、家の中である場合は、玄関からそこまで手で持って運搬できるかどうかチェックが必要です。廊下の広さが 「本体の大きさ+5センチ程度(運ぶ人の手の幅)」 あるか、さらに扉やドアノブなども問題ないかなどを事前にちゃんと見ておきましょう。3.3 セッティングのためのスペース
本体のセッティングに要するスペースは、洗濯機の大きさとピッタリ同じ分確保できればいいわけではありません。もしも壁にピッタリとくっつけておいてしまうと、壁が本体の稼働音を増長させる(ちょうどスピーカーのような役目を果たしてしまうわけですね)ため、音がめちゃくちゃやかましくなるでしょう。 そうなると、共同住居等の場合、近隣の人から苦情を言われることは必須。そうならないよう、また排水用のホースのことを考えても、本体から 左右の壁、奥の壁とそれぞれ一定のディスタンスをキープして配置していく 必要があります。 具体的には本体を置いたとき、スペースをこれだけは確保しなくてはなりません。 ・奥側は壁から5センチ以上 ・排水ホースのある側は壁から9センチ以上 ・排水ホースのない側は壁から2センチ以上 また、洗濯機専用の蛇口が本体よりも上 にあったほうが動作がスムーズです。ただし専用のアイテムをとりつけることで、設置そのものには問題がなくなります。 さらに、ドラム式はとびらの開け閉めにもそれだけの空間的余裕が必要ですから、 「設置はしたけど、とびらが開けられず、使えない」 ということが起きないようにしましょう。3.4 蛇口の形
セッティングをする際は、水栓の種類も チェックしましょう。その種類によっては追加工事や部品を購入する必要があるからです。3.4.1 自動停止装置つき専用水栓
最近の新築建造物には標準的についているタイプです。給水ホースを蛇口にプッシュインするだけでセッティングできます。 さらに、地震などで給水ホースが外れるようなことがあっても、 オートで水がストップする機能 が備わっているので安心です。3.4.2 ワンタッチ専用水栓
こちらも、給水ホースとそのままダイレクトにくっつけることが可能です。ただし外れてしまっても水はストップしません。3.4.3 水栓
いわゆる単水栓と呼ばれるもので、給水用ホースとくっつけるため 専用パーツの取り付けが必要です。3.4 排水エルボがあるか
これは本体と排水口をジョイントさせるためのもの。主にLの字の形です。本来は排水溝に備え付けられているべきものです。もしも新たに引っ越した部屋でこのパーツがついていないのであれば、大家さんや管理会社に言って必ずつけてもらうようにしましょう。 逆に、引越しで去っていくばあいは、排水エルボは新しい家に持って行ってはいけません。必ず残しておくようにしましょう。3.5 排水用ホースがつけられるか
本体と排水口をつなぐためのパーツが 排水用ホース です。たまに本体が排水口より遠かったり、本体と防水パンの間のスペースが十分なかったりすることで、排水用のホースがちゃんとつけられない可能性もあるんです。 ですから、防水パンや本体、さらに排水口がどこにあるかなどを前もって確かめて、ちゃんと排水用ホースをつけられるかチェックしましょう。もし今の状態では排水用ホースがつけられそうにないのなら、洗濯機全体のかさ上げ作業が必要になります。3.6 防水パンの種類と大きさは適正か
防水パン とは、本体の下にあるプラスチック製の板のこと。その中に排水用の穴があいており、それと排水ホースを接続することで洗濯機から水が流されていきます。 もしも本体や排水溝、あるいは排水ホースの問題によって水がもれだすことがあっても、下にこれがあれば、ある程度まで水をキャッチしてくれます。そのため、床が水びたしになって下の階に浸水するような被害をある程度は防止することができるのです。 また、防水パンがあることにより、本体運転時の ガタガタ音 をやわらげる効果も期待できるなど、メリットが大きいです。 本体を設置するのに先駆けて、サイズや形状を 確かめておきましょう。 防水パンは大きく分けて3種類。それぞれについて紹介していきますね。3.6.1 長方形
長方形の形をしており、デコボコのない平らなタイプです。 比較的築年数が経過している住宅に多くみられます。昔の洗濯機は洗濯をするスペースと脱水をするスペースが別々だった二層式が多く、洗濯機本体が長方形だったために、それに合わせた形になっていました。 逆に最近の新しい製品は正方形が多く、設置場所に余裕がうまれるため、設置はおそらく問題なくできるでしょう。3.6.2 正方形
現在、一番多いタイプがこの正方形。排水用ホースを設置しやすくする目的で、周囲が少しかさあげされています。 作業時は、本体を一度仮置きしたときに、手が下にある排水口に届くかどうかをチェックしておきましょう。もし届かなければ、排水ホースを取り付ける際に洗濯機をいったんどかす必要が生じます。 重量のある洗濯機は、大人の男性でも一人では動かすのは難しいため、安全のためにも必ず二人以上で行う必要があります。 こんな移動を何度も行うのはかなりの重労働ですが、下に十分なスペースがない状態で、無理やり排水ホースをつないでしまうのはやめておきましょう。それによって排水ホースがつぶれてしまったり、モーターとホースがぶつかりあって、ホースに穴が空いてしまう危険性があるからです。 このようなときには、次に紹介する 「かさあげ防水パン」の使用がオススメです。3.6.3 かさ上げ防水パン
最新型の防水パンともいえるのはこのタイプです。 こちらはすでに防水パン本体がかさ上げされており、四方のコーナーが高くされているものです。設置後も、手を下に入れやすくなっているのです。だから、排水用ホースのセッティングがやりやすくて掃除もラクだというメリットが。 もし引っ越した部屋にこのタイプがついていたら、「ラッキー」と喜んでください(笑)。4.こんなときはプロを利用し任せよう
設置場所やまわりの状況を確認してみて、以下のようなことが判明。こんなとき、自分でセッティングをする行為にはリスクが伴います。 「せっかくあれこれ苦労して自分でセッティングをしようとしたのに、結局ムリだったので、業者に依頼することになってしまった」 これでは、時間や労力もムダになってしまいます。よほど自信がない限りは、 最初から専門知識をもった業者に相談依頼 したほうがよいでしょう。 ☑排水口がホースとは逆サイドへついている ☑本体かさ 上げの必要あり ☑水栓をチェンジしたい →追加作業が必須となります ☑本体が大きく設置スペースがギリギリである →ただしあまりにギリギリだと、設置のプロにも拒否される可能性あり。 ☑電源差し込み口が届かない ☑アース線がつなげられない →電気にまつわる工事は、法で決められた資格を持つ人にしかできません。 ☑ぎっくり腰の持病がある ☑とにかく自信がない →少しでも不安があるのであれば、決してムリをせず、専門家へ依頼しましょう5.設置手順5ステップ
ここでは、今ある古い本体を取り外す工程から説明していきます。 もしも、新しいものをセッティングするだけならば、 5.3 電源とアースのセットアップから見て下さいね 。5.1 水抜き
以前住んでいた住居からそれまで使用していたものを移動させるのであれば、移動させる前に、 ホースの中に残存している水を完全に抜いて おかなくてはなりません。 これをやらないと、移動中に 水が漏れてきた り、水によって重さのバランスがくずれて思わぬトラブルを招きかねません。移動させる 前の日までにやっておきましょう。 1時間ぐらいでできますよ。 では、作業手順を説明していきます。①洗濯槽の中を空っぽにする
②水道蛇口を閉める
③「スタンダートコース」で洗濯機をスタートさせ、1分たったらストップする
これによって給水ホースの中にある水を完全に抜き出します。④給水用ホースの取り外し
ぞうきんやバケツを準備して、出てくる水へそなえるとよいでしょう。 これで給水ホースの水抜きは完了です。⑤スイッチを入れ最短時間で脱水する
ここからは排水用のホースの水抜きとなります。 まずは脱水作業で洗濯槽の水をしぼりだします。⑥排水用ホースを取り外す
こちらも出てくる水に備え、バケツやぞうきんを用意しておきましょう。 ちなみにドラム式であるなら、排水用ホースの水抜を抜く前に、糸くずフィルターの水を抜きとる作業がプラスで求められるでしょう。5.2 本体の取り外し
水抜きが終わったら、いよいよ本体の取り外しです。①電源を抜く
水にぬれた手で触ると感電の危険があるので注意しましょう。②アース線の取り外し
この作業のためにはドライバーが必要です。水を受けるバケツや大型タオルなどとともに前もって準備しておきましょう。 なお、マンションやアパート等では、入居時についていた 排水エルボ はそのままにしておきます。備え付けの備品を勝手に持って行ってしまうと、後から 敷金として請求されることもあります。5.3 電源とアースのとりつけ
ここからはいよいよ本体のとりつけ作業に入っていきます。 アース線。 これは、家電製品よりもれた電気を地面に流す働きがあり、感電を防止する役目を果たしています。もしこれがないと、漏電等に伴う感電や発火といったリスクを引き起こすため、必ず設置しなくてはなりません。 しかし、線の長さが足りなかったり、電源にアース線を挿す場所がついていなければ、線をつなげることができません。 こんなときは、専門の資格を持った人の手による工事が必要ですから、専門事業者へ依頼するようにしましょう。①電源を差し込む
②ドライバーを用いて、その下にある(ことが多い)設置場所にあるカバーを開く
③専用板をおさえているネジをゆるめ、プレートをうかせる
④プレートの中にある穴にアースの先を入れ込む
⑤ネジをしめ、カバーをもとの位置へ戻す
5.4 排水ホースのセットアップ
10リットル前後の水を一度に使用する洗濯機。そのため適切に排水ホースをセッティングしないと、 規模の大きい漏水 が起きる危険性があります。洗濯機を快適につかうためには、最も大事なプロセスになるでしょう。①元々ついていた排水用エルボを取り外す
もしも、排水用のエルボがついていないなら、必ず管理人さんなどに確認しましょう。前の住民が間違えて持って行ってしまった可能性があります。②排水用のホースとエルボとをくっつける
③エルボを排水口にセットし直す
設置後にくっつけた部分にビニールテープを巻き、上から重ねて結束用のバンドなどで据え付ければ、水もれを防止できるためさらに安心できますよ。5.5 給水用ホースのセットアップ
もしも給水用ホースの長さがギリギリしかないようならば、地震などの際、取れやすくなってしまうのです。ギリギリだったり届かない場合などは 延長ホースを用いましょう。①水道蛇口と給水ホースをつなぐ
②本体に給水ホースをセットアップする
このとき、蛇口が 「オートストッパーつき専用水栓」 であれば、地震などでホースが外れたとき、自動で水を止めてくれます。 しかし、蛇口にこうした機能が備わっていない場合も、止水機能を有する「ニップル」というパーツを取りつければ安心です。6.設置にまつわるQ&A
ここからは、設置に当たってよくある疑問を紹介していきます。6.1 防水パンがないときはどうするの?
築年数の経過した住居などでは、 設置スペースに防水パンがない こともあります。あるいは、 設置スペースがギリギリなので、防水パンが置けない ケースも考えられるでしょう。 もしも防水パンがないと、 ・浸水時に被害が拡大する ・稼働音が大きくなる といったデメリットが発生します。 しかし、防水パンを使用せずに床の上に直接洗濯機を置いたり、あるいは専用の置き台を用いれば、設置すること自体は可能です。 ちなみに、これを使わずに直接本体を置いた場合、 ・本体の周囲をそうじしやすい ・防水パンのサイズを気にせずに洗濯機を選べる といったメリットもあります。6.2 古い本体の処分方法は?
もしも本体がまだ使用できる状態であれば、友人にあげる、あるいはユーズドショップに売ることができます。しかし、使用できないような状態ならば、法に則って適切に廃棄処分を行う必要があります。6.2.1 店に引き取ってもらう
もし家電ショップなどで新しいものを買ったのならば、おそらくサービスで 古いものを引き取ってくれる はずです。最近ではネットで買ったケースでも オプションで古いものを回収してくれること があるので、こうした機会をうまく用いましょう。 新しいものを買っていないケースでも、付き合いの長いお店なら、 有料で引き取っていただくことは可能 であり、所定の手続きも代行してもらえるでしょう。6.2.2 自分で指定場所に持ち込む
輸送手段が確保できるのであれば、自分で 家電リサイクル券を買って、お住いの自治体の 指定引き取り場所に持って行けば 処分してもらえます。 ちなみに、家電リサイクル券は前もって書類に情報を書いておき、所定のお金を払い込んだ上で、 郵便局の受付で受け取る ことができます。つまり、主に平日の昼間という窓口が開いている時間にしか家電リサイクル券は手に入れられませんので、注意してください(そう思うとかなり不便ですよね…)。 こうして家電リサイクル券を手に入れたら、自治体によって指定されている 引き取り場所へ運搬 します。詳しいことはお住いの地域の自治体にて確認して下さい。6.2.3 不用品回収業屋にリサイクル依頼
ちなみに、 「不用品を無料リサイクルしてくれる」という売り手 に依頼するという手もあります。 しかし、なかには後ほどやたらと高いお金を払うよう言ってくる 悪徳業者もありますので、御注意ください。7.トラブルシューティング
せっかく本体のセッティングを終えたのに、いざ使ってみるとなんだか調子が悪い…。こんなケースはセッティングがしっかりとされていないのかもしれません。7.1 排水がちゃんとできていない
排水がちゃんとされていないと、まわりが水びたしになる危険性が伴います。 これは ・十分な設置スペースがなかったためにホースがつぶれている ・ホースの取り付けがゆるかった といったことが原因として挙げられます。 ホースの形状及びとりつけ状況がどうなっているか再確認して修正しましょう。7.2 ガタガタ異音
特に集合住宅では、異音がする状態が続くと周りの部屋とのトラブルにも発展しかねません。 これは ・本体と防水パンとのサイズが不適合 ・本体の4本の足が均等に防水パンに乗っていない といったことが考えられます。 こんなときは、専門家に依頼。あるいはDIYショップやネットで本体のかさ上げのための土台を購入し、セッティングし直す必要があるでしょう。Amazonなどでは安いものなら1,000円台からあるようですよ。8.ぼったくりじゃないおすすめ業者のセレクト法は?
さて、自分でセッティングするのは不安。あるいはやってみたけどうまくいかなかったといった場合は、専門の業者に依頼するという方法があります。 「お店やネットで買ったものならそこに取り付けを頼めばいいけれども、友人からタダでもらったものだから、誰に取り付けを頼んだらよいか分からない」 こんなとき、どのようにして業者をセレクトすればよいでしょうか? 現にyahooの「知恵袋」などにも、 「洗濯機のとりつけを某業者に頼んだら、ネットで買うなら100円ちょっとのパーツのために8000円も請求されてしまった。ぼったくりだったかもしれない」 といった投稿が寄せられていました。 残念ながらこの業界においては、困っておられるお客様の弱みに付け込み、法外な料金を請求するようなぼったくり業者が多数存在するのが事実です。 「じゃあ、ちゃんとネットで調べて、Googleで上位に表示された業者なら大丈夫なの?」 実はこれも、絶対大丈夫とは言い切れません。実はお金を払って上のほうに表示している リスティング広告だけでなく、 普通に上位表示される業者であっても、悪徳業者がちゃんとした(?)SEO対策を施して上位表示させているケースがあるからなんです。 ですので、ここからはぼったくり業者ではない適正業者をいかにしてセレクトするかについて説明していきます。8.1 「指定業者」をセレクト
洗濯機の設置に限らず、蛇口の付け直しや排水のつまりといったトラブルは、やはり水廻りの専門業者に頼むことがなによりも安心です。 そして、信頼できる水廻りの専門業者を見分けるには、ある一つの目印があります。それはいわゆる自治体からのお墨付き、つまり地域の水道局から、 「この業者は一定の基準を満たしており、安心して住民の皆さんの上下水道に関わる工事を任せられるよ」 という認定を受けているかどうかです。 この 認定業者 を知りたいのであれば、お住いの市町村の公式HPにアクセスすれば、事業所名や住所などが分かるはずです。 認定を受けたところには水道局から番号が割り振られます。だから、もし頼もうとしているところが適正がどうか知りたければ 「指定給水装置工事事業者番号を教えてください」 と言えばすぐに分かるでしょう。8.2 複数企業から見積もりを取る
お住いの地域での認定業者が数社ピックアップできたら、次にそれらの業社から相見積もりを取っていきます。その際、必ず見積りが無料である業者を選ぶようにしましょう。 もしも、現場をしっかりたしかめもせず 「洗濯機の設置はすべて500円です!」 といった感じで格安価格を提示するような業者ならば、やはりちょっと怪しい業者である可能性が高く、後から追加で高額な支払いを強いられてしまうかもしれません。 ですので、やはり現場の状態をしっかり確認した上で、確かな見積もりを出してくれる業者が安心です。 また、その際に係員の対応も確認できますので、変に身だしなみが整っていなかったり、態度が悪いようなところは避けたほうが無難なのではないでしょうか。 そのようにして複数の見積りが出そろったら、できれば一番高いところと安いところは除外した上で、依頼する業者を決定するとよいでしょう。9.生活水道センターの場合
ここで、当社について説明をさせていただきます。 当社はもちろん 水道局から指定を受けていますし、 水まわりトラブルに対する年間の対応総実績は約5万件 と、まさに水廻りに関するスペシャリスト集団が集う企業です。 また、北海道から沖縄まで、全国各地に拠点及び協力店を持ち、御連絡いただけば最短15分で御自宅まで急行いたします。 ご用命のお電話は、正月もお盆もGWも一切休みなし。さらに早朝から真夜中まで丸一日中、専門のスタッフが受け付けております。 さらに、料金は全国一律で 基本料金:5000円 +(作業料+材料費) というシンプルな料金体系。このほかにも 各種割引き制度を備えています。
10.まとめ
洗濯機の設置を自分で行いたい人が注意すべき点は以下。 ・設置前の確認をしっかり行う ・特に排水ホースがしっかり取り付けられているかチェックする ・難しいようであれば、ムリせずプロに依頼する関連ページ:
監修者

濱本 孝一 Koichi Hamamoto
代表取締役
2001 株式会社生活水道センター代表取締役就任
- < 資格 >
- 管工事施工管理技士
給水装置主任技術者
排水設備工事責任技術者
ガス消費機器設置工事監督者
ガス機器設置スペシャリスト - 2級ガソリン自動車整備士
2級ディーゼル自動車整備士
美容師
管理美容師
- < 趣味 >
- ピアノ
ムエタイ