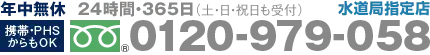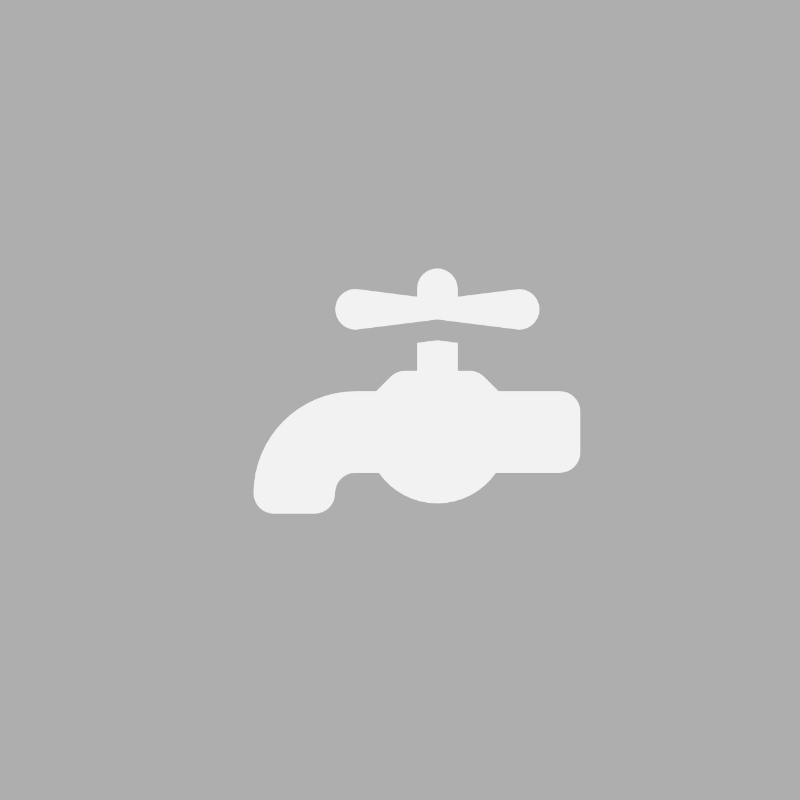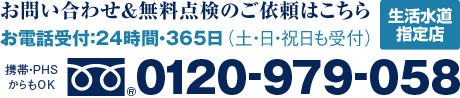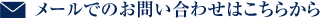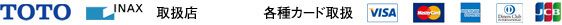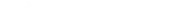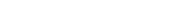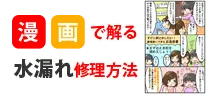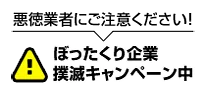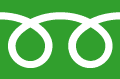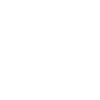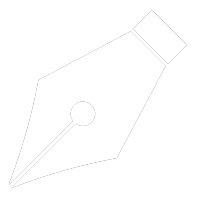
- 投稿日: 2021/09/08
- 更新日: 2024/03/08
トイレの便器交換、一式やってみた!
目次
はじめに
「長年使ってきた自宅のトイレをそろそろ新しくしたいんだけど」 「最新のトイレは節水ができたり、自動的にお掃除してくれるなど便利なものが多いから、そうしたものに交換したいなあ」 「ふたを乱暴にしめたら、便器にひびが入って水がもれるようになってしまったんんだけど、これって便器を交換するしかないんだよね」 「セカンドハウスとして実家をリフォームしたから、そこに新しい洋式便器を入れたいなあ」 こんなふうに理由はいろいろありますが、トイレの便器を新しくしたいという方は少なくないと思います。
でも、便器とトイレ一式を交換するのって、業者に頼むとかなり費用がかかりそうですよね。
こんなとき、もしも自分でトイレ一式を交換できるなら、費用も抑えられるかもしれません。
「でも、便器とかって、個人で買うことはできるの?」 実はできるんです。
インターネットや家電販売店など入手方法はさまざまあります。 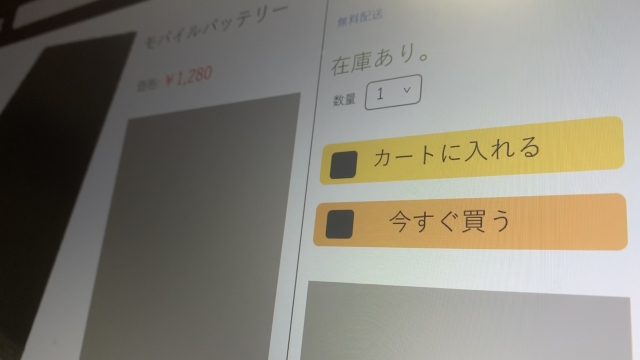
ただ、私たち業者はメーカーから直接買いつけているため仕入れ値で入手できますが、一般の個人の方が購入される場合は、それよりは若干高めの価格になることが多いでしょう。
でも、業者に頼んだ場合の人件費や出張代などが自分でやることで節約できるので、腕に自信のある人はやってみる価値アリです。
そして、トイレの便器等は決して小さなものではありませんので、なるべく作業される日の直近に購入するか、家の中に十分な置き場所を確保してから購入されることをオススメします。 
1 業者とDIY、どちら?
DIYでの便器を新しいものにとりかえる作業へ興味をおもちな場合、自分がやるべきか、あるいは業者に依頼すべきか決めるため、考えるべきポイントが幾つもあります。
まず、刮目すべきなのは、便器の交換作業は、
- 難易度が高い
- 工程が多い
- 工具がたくさんいる
といった特徴があります。
実は当社では、ウォシュレット交換のやりかたにおける記事も載せています。
この記事の最終行にリンクがあります。
少なくともあの作業を余裕でこなせるぐらいでなければ便器一式の交換は難しいと考えてもよいでしょう。
これから紹介する交換作業の工程には、当然シャワー式便座の交換作業もふくまれますが、1記事まるまるつかって説明した工程も、ここでだとかなり簡略化して書いています。
つまり、そうでもしないと書ききれないほどの多くの作業が、便器の交換工程においてはあるということです。
また、ガスバーナーをつかうなど、個々の作業も難易度が高めになっています。
それと、もう一つ注意すべき点があります。
それは、作業している間は、当然ですがトイレが使用できないということです。
トイレが2つ以上あるお家ですとか、普段は人が住んでいないセカンドハウスでしたら、何にちもかけるなどして多少時間がかかるのも問題ないでしょう。
しかし、ご家族の住む御自宅においてたった一つしかないトイレの便器交換をやるんだったら、長くても半日~1日で全作業を終わらせないと、家族の方が困ってしまいますよね。
「絶対に半日で終わらせてみせる! 私、失敗しませんから(by米●涼子)」 ぐらい、腕に自信がある方向けの作業であるということですね。 
2 作業へかかる前に
では、実際の作業に取りかかるまえに、必要となる道具類や、準備しておくべきことについて確認していきましょう。
使う工具
①バケツ&ポンプ…作業におけるさきがけとして便器の水を抜く。
②接着剤(塩ビ管用)…ソケットを取りつけるため。
③ハンマー…いろんな場面で使用。
④電動ドリル…便器の固定金具を取りつける。
⑤スパナ…ナットを取りはずすため。
⑥シールテープ…新しい止水栓に巻きつける。
⑦インパクト…ソケット&ねじを締める。
⑧ラチェットレンチ…便器&トイレタンクの金属部品を取りつける。
⑨パイプソーまたはノコギリ…これまで使っていた排水ソケットを切り取る。
⑩ガスバーナー…古い持ち出し継ぎ手を取り外す。
⑪タオル…水もれに備えて用意しておく。
⑫メジャースケール…便器をどこにおくかをきめる測定用。
⑬モンキーレンチ…止水栓のつけはずし、タンクレバーの固定など、いろいろな作業用。
⑭ドライバー(マイナス&プラス)…ねじしめ及び止水栓の開閉用。
ちなみに、 「電動ドリル等は用意したほうがいいですか」 といった質問を頂戴したことがあるのですが、たしかに、手動のドライバーでもできますが、より早く効率的に進めたいならばあったほうがいいという感じですね。
知人等から借りることができるというならあったほうがよいです。
付属部品の見定め
購入した便器が入っている箱を開けるときは、必要なパーツがちゃんと全部そろっていることを見定めましょう。
また、陶器製ですので、ていねいに取り扱うように心がけましょう。
①位置確認の型紙…便器を取りつけるポジションを確定させるシート。
②排水ソケット…便器の種類によって必要となるものの形が違います。
③固定金具…便器をすえつける金具。
④化粧カバー…便器のサイドに取りつける目隠しとなるもの。
タンクも同様に、事前に部品等を確認しましょう。
こちらも陶器製ですから、取扱いには注意しましょう。
①タンク本体…給水管及びオーバーフロー管などが1セットに。
②止水栓…交換用の止水栓。
古いものを使い回すと、みずもれしたときに保障してもらないので、絶対新しいものへと替える。
③トイレレバー…水を流すためのレバー。
④パッキン…タンクの底に取りつける。
⑤内ふた…トイレタンクの内部に取りつける(ないものもあります)。
これら以外に、 便器から排出された汚水を壁や床の中にある排水管まで運ぶために、これらをつなぐ役割をするのが「持ち出し継ぎ手」というパーツです。
実はこのパーツは便器&タンクには同梱されていませんから、自分で適したタイプを事前にホームセンターなどで用意しておかなくてはいけません。
国産メーカーのトイレでしたら、どこかに品番が示してあるシールが貼ってあるはずですので、その品番をもとに適したものを用意しましょう。
手順を頭にたたきこんでおく
さて、工具もそろい、便器も手元に届いて、さあ、作業を開始…するまえに、もう一つだけやっておくことがあります。
それは事前に便器やタンク等の取扱い説明書や、こちらの手順を熟読して、作業の流れを頭にたたき込むことです。
作業の順序はもちろんのこと、どのような作業であるか、またこれは何のために行うものなのか、使う道具はなにか、どこに注意するかなど、事前にしっかりとイメージを描いておくことで、工程の流れがスムーズになることでしょうし、万が一、異常がおきてしまったときもすぐに気がつき対応ができるでしょう。
補足して
補足ですけれども、作業中いろいろな工具を使うため、危険防止の観点からも小さなお子様やペットが近くにくることがないよう環境を整えてください。
そして、トイレや廊下にエアコンがついているという御家庭は少ないと思いますので、夏の暑い日に作業をするときは、換気をよくし、水分補給をこまめに行って熱中症を予防しましょう。
さらに進行中、万が一、外部配管より水が逆流するようなことがあったら大変ですので、台風及びゲリラ豪雨といった大雨の降る予報が発令されたときは作業をしないでくださいね。
3 トイレ一式を交換してみた!
いよいよ実際の作業のスタートです。
まずは、古い便器を取り外すところからです。
【工程1】便器の取り外し
①止水栓を閉める
まずトイレの止水栓をクローズさせましょう。
ドライバー、あるいはハンドルを右回転させて給水を絶つのです。
このとき、回した回数をメモすれば後ほど役立つでしょう。
②水を抜く(タンク&便器)
レバーハンドルを10秒程度ひねりっぱなしにしてタンクから水をだしきります。
もし水が残っていたりすると、タンクを取り外した時に水が漏れてしまうので、完全に抜き切るようにしましょう。
念のためトイレタンクのふたをオープンし、トイレタンク内に水がないのを目視チェックすれば完璧ですね。
そのあと、便器内の水を給水ポンプでくみだしてバケツへ入れておきます。
こちらも水が残らないよう作業します。
③ウォシュレットを外す
ウォシュレットがついていたら、便器のセットオフ前にまずこちらからとりましょう。
まず止水栓にリンクする分岐金具のナットをモンキーレンチで取り外しましょう。
続いて分岐金具と、トイレタンク及びウォシュレットからの給水管をつなぐナットも外しましょう。
ベースプレートを使うタイプならば、本体はひとおしすれば外すことができるでしょう。
タイプによってやり方が違いますので取扱い説明書にしたがい取り外しましょう。
もし手元になければメーカーのホームページでも見られますよ。
※詳しくは最終行リンク先を参照ください。
④タンクのふたを外す(外ふた&内ふた)
つぎにトイレタンクを取り外します。
最初にタンク上部にある外ふたを外し、種類によって内ふたがついているものもあるため、これも取り外します。
⑤給水管よりタンクを外す
トイレタンクの給水ホースは、給水管にナットにてすえつけられています。
ですから、モンキーレンチを使って接続を解除します。
止水栓を閉めているので管から水が出ることはないでしょうが、ホース内に水が残っている場合があるため、取りかかる前に下にタオルをしいておきましょう。
⑥タンクを撤去する
トイレ本体とトイレタンクをすえつけてあるボルトをモンキーレンチで取り外します。
便器の裏側に2つ固定箇所があるので、2つとも行ってください。
ボルトを取り外せば、持ち上げて取り外しができるでしょう。
トイレタンクは、作業をさまたげないような場所へ移動させるとよいですね。
⑦便座を外す
続いて、便座をすえつけている金具を取り外します。
便器のわきにくっついている化粧カバーを取りのぞけば、金具のありかがわかるでしょう。
(トイレのタイプによってはこれがついていないことも) そのあと左右2か所に設置されている固定金具の取り外しです。
ノーマルタイプだったら固定金具が外れれば取り外しできるでしょう。
ウォシュレットがついていると作業運びが少しちがうため、最終行のリンク先を参考にして下さい。
⑧本体を取り外す
タンクおよび便座をやりおえたら、続いて便器本体をやっていきます。
最初に便器をすえつけている金具のカバーキャップをとります。
便器の型により、ネジの場合とナットの場合があるので、それぞれ適した工具によってはずします。
それらの金具を取りのぞけば本体を床から取りはずせる状態になります。
便器は90キロ前後とかなり重いので、割れないように慎重に動かしましょう。
ちなみに、古い便器の処分方法ですが、業者さんに交換を頼めば、作業後にそのまま引き取っていってくれますが(産業廃棄物として処理されます)、個人で便器の交換を行った場合は、原則、袋の中に入れて、それを外から砕いて粉々にした状態で不燃ごみとして処分することになるでしょう。
詳しい処分方法については、お住まいになっている自治体へ問い合わせるなどルールに従って行いましょう。
【工程2】排水ソケットの取り外し
ひきつづき、古い排水ソケットを取り除く作業をします。
ガスバーナー及びパイプソーといったやや高度な作業もあります。
①ネジを外す
便器を取り除いたので、トイレの排水口にリンクする排水ソケットが露出しました。
これを撤去しましょう。
最初に床についている排水ソケットのすえつけ用ネジを取り外しましょう。
②パイプを切る
次に、排水ソケットの床から飛び出たパーツを、パイプソーもしくは鋸等を用いてカットします。
くれぐれもケガのないよう注意してください。
③ガスバーナーでとかす
カット終了後、パイプの一部分はまだ床の下にある状態です。
このパイプは接着剤でくっついていて、そのままでは取れないためバーナーを使ってパイプを溶かす工程が必須となるんです。
あぶり過ぎるとパイプ(塩化ビニール)が燃えてしまい、部屋のなかにくさいにおいが大発生するので注意しましょう。
④パイプを取り出す
バーナーでしばらくあぶることで接着剤が溶け出しパイプが変形します。
排水ソケットをマイナスドライバー等の道具を用いて引っぱりはがします。
くれぐれもやけどには注意しましょう。
あと、この際に排水口に道具やネジを落とさないよう気をつけて下さい。
【工程3】止水栓の取りつけ
これまで使っていた古い止水栓を取り外し、トイレタンクに同梱されていた新しいものへつけかえる工程です。
「同じメーカーだったら、古いパーツでも問題なく使えるんじゃない?」 と思われるかも知れません。
しかし、トイレ本体をあたらしくする場合、いっしょに止水栓も新しい物へチェンジしないと、水漏れが起きたときに補償が受けられなくなってしまうというルールがありますので、必ずこの作業はスルーせずにちゃんとやりましょう。
①水道の元栓を閉める
止水栓の取りかえ作業に着手する前に、必ず水道メーターボックスにある元栓を閉めましょう。
これをしめると家全体の水が出なくなりますから、同居のご家族には事前にちゃんと連絡しておきましょう。
元栓をしめないままで止水栓を取り外すと、噴水のように水が噴き出すので、必ずこのプロセスを忘れずに行ってください。
②止水栓にシールテープを巻く
これからとりつける新しい止水栓にシールテープを巻きます。
巻きつける前に、止水栓についているゴミや汚れをタオル等でていねいにふき取りましょう。
ゴミ等が残るままだと、テープと止水栓の間にスキマができ、水がもれる要因となってしまうからです。
そして、テープのほうも、先っぽをはさみなどでまっすぐにカットしておきます。
こうすることで、作業中にテープがねじれることを防ぐのです。
ちなみにテープは、止水栓の端っこからびっしり巻いてはいけません。
先端のネジ山2つほどを残す感じでスタートさせるとよいでしょう。
これも、つまりや水もれを防止するためです。
そして、かならず時計まわりにまきつけるようにします。
もしも、巻いている途中に少しでもテープがずれたりよれたりしたら、ためらわずにやり直してください。
そのまま続行してしまうと、後から水もれの原因になってしまいます。
だいたい10回前後がめやすで、たくさんまけばいいというものでもないのです。
これは意外とコツがいる作業で、これができたからといって女性にモテるわけではありませんが、修理業者からは一目おかれるかもしれませんよ(笑)。
といいますのは、シールテープ巻きは洗濯やキッチン、洗面所などのありとあらゆる部分における水道蛇口などの交換作業にはかならずついてくる作業だからです。
そもそも、どうしてシールテープというものをわざわざ巻きつけなくちゃいけないんだといえば、これは金属製の配管の部品と部品の間にできるわずかなすきまをうめるため、とてもたいせつな役割を果たすからです。
そして、シールテープにはいくつかメーカーがありますが、基本的にはどれを使っていただいても作業には問題ないと思います。
それより、テープをていねいにきっちりまくことが大事ですね。
テープを巻いたあとは、指のひらでぎゅっと押さえて全体をなじませます。
巻き作業に失敗した場合のことなども考慮し、シールテープは多めに用意するとよいでしょう。
③古い止水栓を取り除く
止水栓は、たいていトイレ室内の奥の方に設置されていますので、モンキーレンチで反時計回りに回して外します。
外したあと、ネジ山へ残存するシールテープがあれば、完全除去しましょう。
これがそのままだと、おNEWの止水栓をつけた際に水がもれてしまうかもしれないからなんです。
④新しい止水栓を設置する
新しい止水栓の取りつけを行います。
レンチを使い、最後まで閉め切るようにします。
そして、止水栓の給水口を奥側に向けるように閉めると、給水ホースを取りつけやすくなるでしょう。
⑤新しい止水栓を閉める
新しい止水栓は、この段階ではまだ閉めておきます。
止水栓を閉めたならば、家全体の元栓を開いても大丈夫です。
御家族にもちゃんと連絡しましょうね。
【工程4】便器のセットアップ
ここでは排水ソケットを新設し、便器を取りつけるまでの一連の工程です。
ここへくればもうひといき!
①ソケットサイズをたしかめる
排水口をチェック後、管の太さや直径にあわせとりつける持ち出しソケットサイズを再確認しましょう。
一般的には4種類のソケットが市販されていますが、その中から最もぴったりのものがあらかじめ用意されているはずです。
ちなみに、排水ソケットは便器のある状態だとどのような形であるかは分からないので、生活水道センターでは常に幾つかの種類を営業車へ積んでいるんです。
これがけっこうやくだちます。
②ソケットを設置する
持ち出しソケットに専用の接着剤を塗布後、排水口へセットします。
③ソケットをカットする
パイプソーもしくは鋸にて、持ち出しソケットを床から高さ6センチほどにカットしましょう。
許される誤差はプラスマイナス5ミリ以内です。
④型紙シートをセットする
次に、便器をセットするポジションを決めるため、付属の型紙シートをソケットに合わせて配置します。
⑤位置をマーキングする
型紙ではどこにネジを取りつけるかを確かめることができて、作業しやすいよう、油性ペンで印がつけられるようになっています。
型紙シートは実際にネジや便器を取りつける時外すため、シートの指示に一致するべく印をつけ終わったら役目が終了いたします。
⑥ソケットをつなぐ
排水ソケットと持ち出しソケットに接着剤を塗布してつなぎあわせましょう。
⑦トイレ用固定具をつける
さきほどマーキングシートを使って印をつけた位置に、付属の便器用金具をつけます。
トイレの前方部分もさきほど同様、施工しましょう。
⑧便器を設置する
つけた固定具の上より便器全体をかぶせるかんじで配置を行いましょう。
⑨正面からも固定する
本体の配置が終了したら、便器の後ろ側の固定金具の取りつけをすすめましょう。
便器は丈夫そうに見えても陶器製ですので、強くしめすぎるとヒビが入る危険性があるので注意してください。
電気工具であるインパクトドライバーを使ってネジをしめるのであれば、しめすぎないためにも、8割ほどで作業をやめて、残りは手動のドライバーで閉めるようにしましょう。
こうすれば陶器が割れるのを防ぐことができます。
最後にキャップをつければ、便器の設置作業はおしまいです。
⑩便座(ウォシュレット)をとりつける
次に便座、もしくはウォシュレットをセットアップします。
便座の場合は、便座にある差し込み口に便座プレートを指します。
それを裏側からナットでとめ、プレートに便座を差し込んでロックすれば完成です。
ウォシュレットをつけるなら、それにさきがけてベースプレートを便器の上へねじにて固定することではめ込みます。
※くわしい設置のやりかたについては、最後のリンク先にて詳しく紹介しています。
【工程5】関連部品のセッティング
①タンクを組み立てる
次に新しいトイレタンクをセッティングします。
まずトイレタンク外側部分に本体をはめ込みます。
陶器製の外側部分への傷つ防止の目的で、下に敷物をしき、本体を横へ寝かせて行います。
トイレタイプによってやや外形がちがうので、タンクに付属する取扱い説明書でよく確認しましょう。
②接続棒を取りつける
タンクの下部分の穴へ、トイレ本体とつなぐための棒をセットしましょう。
③底にパッキンをつける
タンクから水がもれないよう、トイレタンクの底へパッキンをセットします。
④タンクを設置する
組み立てたトイレタンクを持ちあげて、便器本体後部の穴に合わせるようにして置きます。
そして、タンクの底部分の取りつけボルトに、下側から固定ナットを使って固定さします。
この工程は工具はつかわず閉めるとよいでしょう。
⑤レバーを取りつける
トイレタンクにレバーの取りつけをし、内側よりナットにて閉めてすえつけましょう。
トイレレバーは水漏れの原因になりやすいパーツですので、手で仮締めしてから、後で工具を使ってしっかりと閉め直します。
⑥本体とレバーを接続する
タンク本体とトイレのレバーをつなぎます。
レバーを動かしたときにちゃんとタンクより水が出れば成功です。
⑦タンクの内ふたを取りつける
トイレタンクの上部に内ふたを取りつけましょう。
この作業も簡単で工具は不要です。
軽く上部へ乗せる感じがよいでしょう。
⑧手洗い管を設置する
手洗い管を(付属のない製品も有り)トイレタンク外ふたにセットしてから下側からナットにて固定しましょう。
⑨外ふたを取りつける
外ふたをタンクの上におく感じでセットアップすればおしまいです。
⑩付属品を取りつける
サイドカバーがあるタイプならば、これを便器に取りつけます。
はめ込むかたちで設置ができます。
⑪テストする
ここまでの一連の工程が終わったらいよいよテストです。
止水栓の元栓をオープンし、タンクに水を入れてみます。
このとき、タンクや給水管より水のもれがないか確認し、とくに問題ないなら作業完了です。
4 お困りの際は生活水道センターへ
こうして一連の便器一式をあたらしく取り換える作業をご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
実は、実際の施工現場では、思わぬトラブル等により、ここに書いた以外の作業が発生することもあります。
例えば、古い便器を取り外すときに、便器が床にくっついてしまって、取れない状態になっていたり。
むりにはがそうとすると床がこわれてしまうのでなかなか難儀しました。
あるいは、便器を取り外したら排水の管が立ちあがっているはずなのですが、これがなかったりして、想定外のオプション作業が要求されることもあるんです。
さらに前に施工した人がまちがえたのか、あるいは知らずにやってしまったのか、はたまたいやがらせ(?)なのかわからないんですけど、排水ソケットと排水管、この2つのパーツが接着剤にてガンガンに固められてて、取り外そうとして非常に苦労した経験なんかもあります。
とはいえ、私たちはプロですので、現場で想定外のことが起こっても、なんとか対応できます(たまに電話で先輩社員に教えてもらうことはありますが…)。
まあ、次のお客様のところへおうかがいする予定がつまっていますと、内心けっこうあせるんですが。
これが一般のお客様ですと、どうしてよいか分からなくなってしまうこともあるのではないでしょうか。
さらに、現在の規格では、洋式便器は150キロまでの体重を支えることができるようなつくりになっているため、陶器便器はその重さが約90キロ、最近の比較的軽い樹脂便器でも80キロはあります。
さらに、トイレタンクも40キロから50キロぐらいの重さがあるみたいです。
こんなすごい重量を一人で持ち上げたり動かしたりしようと思うとかなりの力が求められますし、作業中に腰を痛めてしまう可能性もありますよね。
さらに、うまく持ち上げられなくて落としてしまったりして、ケガをしたり、陶器製の便器がひび割れて使い物にならなくなることも想定できます。
こういったことを考えると、実際に作業を進めておられる途中で、 「あ、これはちょっとムリかもしれないな」 と感じられることもあるかもしれません。
この先の作業を進めるのはちょっと難しい。
でも、これ以上時間がかかると、同居の家族がトイレを使えなくて困ってしまう。
こんな、進むことも退くこともできないような袋小路に直面する可能性もあります。
そんなときは、決して無理せず、私ども生活水道センターまでご連絡ください。
たとえ作業の途中であっても、あるいは予期せぬトラブルがあっても、私どもがプロの経験と技術力で責任を持って作業を遂行いたします。
お困りになった際は、ご連絡が早ければはやいほど、後の作業も楽になります。
それにこの一連の便器交換作業は、プロであっても新人のうちは内心胸がドキドキするほどの難作業です(もちろんそんな新人には、もれなくベテランがペアとなって派遣されるので、お客様に御迷惑はおかけしませんよ)。
一般のお客様が作業を途中でストップされることがあったとしても、なんら不思議ではなく、恥ずかしいことでもなんでもないです。
(逆に、この作業が楽にできたよ、という方がおられましたら、ぜひ弊社にスカウトさせていただきたいほどです)。
ですからなにかこまったことがあったらいつでも、生活水道センターまで御連絡してくださいね。
※詳細なウォシュレット交換手順をしりたいならここへ
監修者

濱本 孝一 Koichi Hamamoto
代表取締役
2001 株式会社生活水道センター代表取締役就任
- < 資格 >
- 管工事施工管理技士
給水装置主任技術者
排水設備工事責任技術者
ガス消費機器設置工事監督者
ガス機器設置スペシャリスト - 2級ガソリン自動車整備士
2級ディーゼル自動車整備士
美容師
管理美容師
- < 趣味 >
- ピアノ
ムエタイ